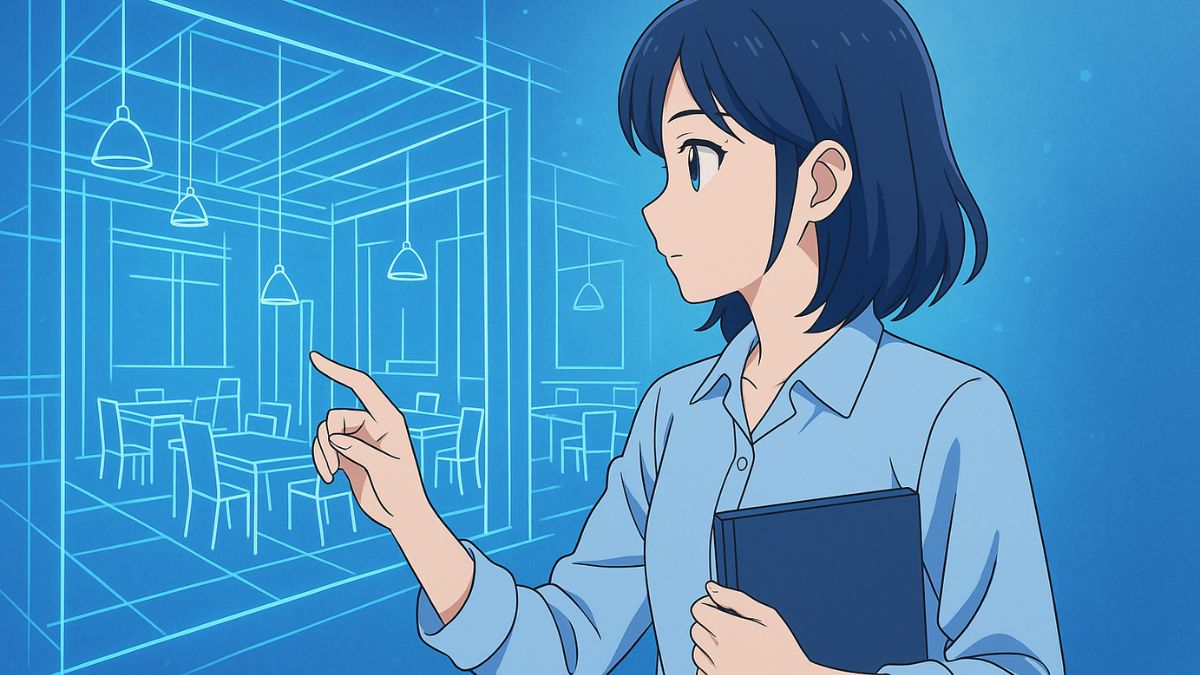台湾で店舗を出店したいと考えている日本企業が年々増えています。
しかし、「設計は任せておけば大丈夫」と思っていたら、思わぬトラブルに発展してしまったという声も少なくありません。
この記事では、日本と台湾、それぞれの店舗設計における考え方の違いから、設計段階で起こりやすい5つのトラブルを紹介します。
実際の現場のリアルな視点から、日本企業がどのようにすれば台湾の設計会社とスムーズに仕事を進められるかを、具体的な事例とともに解説しています。
「図面文化の違い」「意思疎通のコツ」「現場対応の柔軟さ」など、日本人が見落としがちなポイントを知ることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができるはずです。
図面が完成しないまま工事が始まる(台湾特有の“走りながら考える”文化)
設計未確定のまま進む理由とは?
台湾では「走りながら考える(邊做邊改)」という文化が、店舗内装の現場に深く根付いています。
これは、スピードを最優先する台湾特有のビジネス慣習から生まれたもので、図面が完全に仕上がる前でも工事がスタートしてしまうことが多くあります。
その背景には、台湾のテナント契約の事情もあります。
賃貸契約を結んだ瞬間から家賃が発生するケースがほとんどで、「一日でも早くオープンして売上を立てたい」という強いプレッシャーがオーナーやデベロッパー側にあるためです。
さらに、設計者と施工者が一体化しているケースも多く、現場で設計の意思決定をその場で行うことが容認されています。
これによりフレキシブルな対応が可能になる一方で、日本企業からすれば「なぜ図面が揃っていないのに始めるのか?」という大きな不安材料になるのです。
このような進め方は、日本の「段取り八分、仕事二分」という文化とは大きく異なります。
日本では、詳細な設計図面が完成し、それを元に正確な見積もりや工程管理が行われてから工事に入るのが常識です。
日台のこのギャップを知らずにプロジェクトを進めると、現場で「そんな指示は聞いていない」「図面がまだ来ていない」といった混乱が発生し、信頼関係の損失にもつながりかねません。
現場主導の柔軟対応が生む混乱
台湾では、工事現場の職人や現場責任者が「長年の経験」をもとに判断し、設計者に確認せずにその場で対応を変えることもあります。
たとえば「この材料は手に入らなかったから、代替品でやっておいたよ」といったような変更が、特に連絡もなく実施されてしまうケースです。
日本の感覚からすれば、これは大きなトラブルの種になります。
しかし台湾側からすると、「現場判断で進めること」はむしろ効率的で信頼されるスタイルと捉えられています。
このギャップが設計段階で顕著に現れるのが「図面上に書かれていない部分」の処理です。
日本では細部に至るまで設計者が指示を明確に出し、施工側はその通りに実施するのが基本。
しかし台湾では「そこまで指示がないなら、自分たちでベストだと思う方法を選ぶ」という判断が日常的に行われます。
結果として、完成した空間が「思っていたのと違う」というトラブルに発展する可能性が高くなります。
日本企業にとっては、現場での判断や材料選定の自由度の高さに驚かされるでしょう。
そのため、設計段階で「ここは絶対にこうしたい」というポイントを明確に伝え、記録として残すことが極めて重要です。
そうでなければ、台湾式の現場判断があなたの理想の空間を予想外の方向に変えてしまうこともありえます。
日本企業が見落としがちな確認プロセス
日本の設計プロセスでは、詳細図面やパース(完成イメージ図)などを使いながら、施主と設計者、施工者の三者で納得のいくまで確認作業を行うのが一般的です。
これは「やり直しコストを最小限にする」ための重要な工程と考えられています。
しかし台湾では、こうした細やかな確認プロセスを経ずに「早く形にしてしまおう」と進行していく傾向があります。
これにより、完成直前になって施主から「ここ、こんなはずじゃなかった」とクレームが出る事態が少なくありません。
日本企業が台湾のプロジェクトに参加する場合、この確認プロセスを「日本側でリードする」姿勢が必要です。
打ち合わせ時に必ずチェックリストを活用し、「未確定事項」を明示すること。
また、重要な部分は必ず「3Dイメージ」など視覚的に共有できる方法を用いることで、認識のズレを最小限に抑えられます。
「とりあえず進めよう」にどう対処するか
台湾現場で頻繁に聞かれるのが「先にできるところから始めてしまおう」という判断です。
図面が出ていない部分でも、「あとで修正すればいい」と安易に着手してしまう姿勢があるため、日本企業としては非常に神経を使う場面となります。
このような判断に対しては、プロジェクトの初期段階で「未確定事項には手をつけない」というルールを共有し、合意しておく必要があります。
また、現場の進捗報告はできる限り毎日確認し、変更が起きた場合は即座に図面や資料に反映する“変更履歴管理”の体制を整えることが有効です。
プロジェクトマネージャーや設計監修者が、日本側と台湾現場の間に立ってブレーキ役を果たすことも、トラブル防止には欠かせません。
図面完成前に契約?リスクと対策
台湾では、まだ図面が完成していない段階で工事契約を結ぶことも珍しくありません。
これは、日本企業にとって非常にリスクの高い状況です。
なぜなら、設計が確定していない状態では、金額・仕様・工程すべてが不確定要素に満ちており、あとからの変更によって追加費用が発生する可能性が高いためです。
そのため、日本企業が台湾でプロジェクトを進める際は、契約書に「設計が確定してから工事を着工する」と明記することが重要です。
さらに、「設計変更時の対応フロー」や「追加費用の事前合意ルール」も明文化しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
施主と設計者の合意が取れていないまま施工へ(双方の意識のズレ)
台湾における「確認」とはどういう意味か?
日本の設計現場では、「確認済み」といえば、「施主が図面やパースを見て内容を理解し、合意した」状態を指します。
しかし台湾では、「確認した」と言っても、その意味合いがやや曖昧なことが多く、実際には「だいたいOK」「細かいところは後で話そう」といった緩やかな合意で進んでしまう場合があります。
この文化の違いが、設計者と施主の間で重大な認識のズレを生む原因になります。
たとえば、日本企業の担当者が「細部のディテールも確定した」と考えていたにもかかわらず、台湾側は「大枠は決まったけど、あとは現場で見て判断しよう」と受け止めていた、というようなことがよく起きるのです。
この違いを乗り越えるには、「確認済み=書面化・ビジュアル化されている」という共通認識を事前に築いておくことが大切です。
図面へのサインや、メールでの明確な承認記録など、「曖昧な確認」を避ける工夫が求められます。
デザイン変更の伝達ミスによる現場混乱
台湾では、施主から設計者へのデザイン変更の指示が、口頭やLINEメッセージなどで非公式に伝えられることが多くあります。
このような連絡方法はスピード感がある反面、情報の抜け漏れや誤解を生む原因になりやすいです。
たとえば「カウンターの高さを5cm下げたい」という変更指示が図面に反映されないまま、現場に伝わらず、完成後に「話が違う」とトラブルになることも。
こうしたミスは、確認方法がシステマチックでない台湾ならではの構造的な問題です。
日本企業がこの状況に対応するには、情報の共有ルートを1本化することが効果的です。
たとえば、すべての設計変更は専用フォーマットで提出し、関係者全員の確認が取れるようにクラウド管理するなど、変更内容の「見える化」と「履歴化」を徹底することで、トラブルを大きく減らすことができます。
「口約束」の落とし穴と記録の重要性
台湾では、人間関係を重視する文化が強く、「信頼関係があれば、細かいことは言わなくても通じる」という価値観があります。
このため、口頭のやりとりや非公式な合意でプロジェクトが進んでしまうことが珍しくありません。
しかしこの「口約束」は、いざトラブルが発生した時に証拠として残らないため、責任の所在が曖昧になります。
日本企業の担当者が「確かに言ったはず」と思っていても、台湾側は「聞いていない」「そんなつもりではなかった」となるケースも多く、関係性がこじれる原因となります。
トラブルを防ぐためには、記録を残す習慣を徹底することが不可欠です。
たとえば、打ち合わせ後には「議事録(Meeting Memo)」を日英中3言語で作成し、関係者全員にメールで共有するだけでも、合意事項の誤解を防ぐ効果は大きいです。
打ち合わせ記録を残す日本の常識を台湾でどう活かすか
日本では当たり前の「議事録文化」は、台湾ではまだあまり一般的ではありません。
そのため、打ち合わせ後に記録を作成・共有しても、「そんなものは読まない」「細かすぎて面倒」と受け止められてしまうこともあります。
こうした状況に対応するには、「読みたくなる議事録」を工夫して作成するのがコツです。
要点を3〜5行にまとめたダイジェスト版、図やイラストを多用した視覚的資料、確認事項にチェック欄を設けるなど、形式にとらわれない柔軟な工夫が、台湾の現場では高く評価されます。
また、LINEなどでやりとりされた内容も、必ず正式な資料にまとめて再共有することを習慣化すると、万が一のトラブル時にも安心です。
合意形成に必要な“可視化”の工夫
日本と台湾で設計意図を共有するうえで最も有効なのが「可視化」の徹底です。
図面だけでなく、パース、CG、モックアップ、マテリアルボードなど、あらゆる視覚情報を用いて、「言葉のズレ」を防ぐことが極めて重要です。
たとえば、台湾のクライアントは「シンプルなデザインがいい」と言っても、日本人が考える「シンプル」とは意味が異なることが多々あります。
こうした曖昧な言葉を具体的にすり合わせるには、事例写真や実際の素材を見ながら話すのが最も確実な方法です。
さらに、設計図面にイラストやピクトグラムを挿入し、誰が見ても同じイメージを持てるようにするなど、設計内容のビジュアル補強を行うことで、台湾の現場でも驚くほどスムーズに意思疎通が進みます。
設計図の情報が不足している(日本の“丁寧すぎる”図面との違い)
台湾ではなぜ簡易図面が主流なのか?
台湾の設計現場では、詳細な図面よりも「概要を示す簡易図面」が主流です。
これは、スピード優先の文化と、現場で柔軟に対応できるという前提があるからです。
特に、内装工事では設計者と職人の間に「長年の経験と阿吽の呼吸」があり、細かい指示がなくても通じるとされる場面が多いのです。
一方で、日本では寸法や納まり、仕上げ材、構造的な収まりに至るまで、細かく指定された図面が必要とされます。
日本企業が台湾設計会社に発注する際、この図面の情報量の差に驚くことが多く、「図面の情報が足りなすぎて、見積もりも出せない」と感じる場面もしばしば発生します。
台湾側から見ると、「これくらいで十分でしょ?」という感覚で出してくる図面に対し、日本側は「リスクだらけ」と受け止める。
このすれ違いを放置しておくと、後に大きなトラブルへ発展してしまう恐れがあります。
情報不足による現場判断の連続
台湾では、設計図面の不足を現場の判断力でカバーするという慣習があります。
つまり、「ここに詳細図がないなら、自分たちで考えてやる」という対応です。
しかし、日本企業が想定するデザイン意図や品質基準が現場に伝わっていない場合、意図しない形で仕上がってしまうリスクが非常に高くなります。
たとえば、什器の納まり、床材と壁材の切り替え部分、照明器具の配置といった微細な部分で、「日本側の常識」と「台湾現場の常識」がズレていることはよくあります。
このズレは、仕上がったあとでは修正が難しいため、事前に補足資料や「気をつけるべきポイント一覧表」などを用意し、台湾側と共有しておくことが重要です。
施工品質に直結する“曖昧な指示”
台湾現場では、「この壁は白っぽくていい感じで」といった曖昧な指示でも、現場の職人がそれなりに仕上げてくれる文化があります。
しかし、その“それなり”が、日本の品質基準と一致しているとは限りません。
たとえば、同じ「白い塗装壁」でも、日本ではマットな仕上げを想定していたのに、台湾では光沢感のある塗装を選んでしまった、というケースは少なくありません。
これは、図面や指示が具体的でなかったことが原因です。
このような事態を防ぐには、設計図面に加えて「仕上げサンプル」や「施工写真付き指示書」を併用することが有効です。
現場の職人が視覚的に理解できるようにすることで、期待した品質に近づけることが可能になります。
詳細図を求める日本企業への対応方法
台湾設計会社にとって、日本企業の求める「詳細図」は非常に手間がかかるものであり、追加費用を請求されるケースもあります。
そのため、詳細図の作成を依頼する際は、「どの部分の図面を、なぜ必要とするのか」を明確に伝えることが重要です。
全ての図面を詳細化するのではなく、「品質に直結する箇所」「設計意図を正確に伝える必要がある箇所」を優先し、優先順位を明示しましょう。
また、詳細図の代わりにモックアップ(試作品)や1部屋だけの試し施工で品質を確認するという方法も、台湾では非常に効果的です。
設計事務所との良好な関係を維持しながら、品質確保の要望を伝える“交渉力”が、日本企業側に求められるポイントです。
図面に頼りすぎない「現場設計力」とは
台湾でプロジェクトを成功させるためには、「図面通りに仕上がらない前提」で設計を進める柔軟性も必要です。
つまり、図面はあくまで“設計の方向性”を示すものであり、最終的な完成形は現場で微調整されながら実現されるという考え方です。
このときに重要になるのが、日本側担当者の「現場設計力」です。
現場で起きる小さなズレや判断をその都度キャッチし、適切な判断と指示を出せる人材がいることで、図面に頼らなくても品質の高い空間を作ることができます。
そのためには、日々の現場写真チェック、定期的なビデオ通話、工程ごとの進捗確認ミーティングなど、「現場とつながる仕組みづくり」が欠かせません。
法規制の理解不足による設計修正(消防・建築法規の違い)
日本と台湾の法制度の違い
日本と台湾では、内装に関わる法規制の構造が大きく異なります。
日本では、建築基準法や消防法などに基づいて、明確なルールとチェック体制が整備されており、設計段階で事前確認を行うのが常識です。
一方、台湾では「図面を出してから申請を通し、修正があれば現場で対応」という後追い型の制度運用が主流です。
特に消防法規に関しては、設計完了後の消防申請(消防送審)で初めて詳細な指摘を受けることも多く、日本企業にとっては「なぜもっと早く教えてくれなかったのか」と戸惑うポイントとなります。
この違いは、設計の考え方やプロジェクトの進め方そのものに影響を与えるため、事前に台湾の法制度について最低限の理解を持っておくことが必要です。
設計が完成してからの「やり直し地獄」
台湾の消防検査は非常に厳格で、提出した設計図面に不備があれば、すぐに「退件(差し戻し)」となります。
問題は、この差し戻しが設計の根幹に関わるような指摘になるケースが少なくないことです。
たとえば、非常灯の位置、スプリンクラーの配置、避難導線の確保など、意匠と相反する要求が出ると、それまで完成していたデザインを一から描き直さなければならなくなります。
この「やり直し地獄」は、日本企業にとって時間的・金銭的に大きなダメージとなります。
特に、開店スケジュールが差し迫っている状況では、「間に合わない」という事態も現実に起こります。
そのため、設計段階で「消防基準を満たすこと」を前提に設計を行い、申請経験のあるパートナーと組むことが重要です。
消防検査の落とし穴とその対策
台湾の消防検査で特に注意すべきポイントは以下の通りです:
| 検査項目 | よくある指摘内容 |
| スプリンクラー | 設計位置と天井構造の干渉、カバー範囲の不足 |
| 非常灯・誘導灯 | 高さ不足、視認性不良、設置数不足 |
| 消防制御盤 | 壁内埋設がNG、設置位置が不適 |
| 火災報知設備 | 壁材との干渉、配線の不備 |
| 避難通路の確保 | 障害物の設置、導線の明示不足 |
これらの項目は、設計の初期段階から検討しておく必要があります。
さらに、工事開始前に「消防顧問」と呼ばれる専門家による事前レビューを依頼することで、申請段階での差し戻しを大幅に減らすことが可能です。
台湾設計会社が見落としがちなポイントとは
台湾の設計会社でも、消防検査の存在は当然知っていますが、プロジェクトの初期段階から意識しているとは限りません。
特に小規模な設計事務所では、「どうせあとで直すから」と軽視されがちです。
そのため、日本企業の側から「消防送審対応済みの設計でお願いしたい」「事前に消防顧問を入れて設計確認を行いたい」と明示することが重要です。
こうした要求を出すことで、設計者も初期から法規対応を視野に入れた設計を意識するようになります。
また、消防図面(消防図/系統圖)を別途作成することを前提にスケジュールを組むことも、非常に現実的な対策です。
法規対応に強いパートナーの見分け方
台湾で設計パートナーを選定する際、「デザインが良い」だけでなく、「法規対応にどれだけ慣れているか」を見ることが重要です。
その判断基準のひとつが、以下のようなチェックポイントです:
- 過去の消防検査対応実績があるか?
- 消防顧問と連携した設計体制があるか?
- 消防送審までのスケジュールを逆算して設計しているか?
- 法規に関する説明を具体的にできるスタッフがいるか?
これらを事前にヒアリングすることで、「信頼できる設計会社」かどうかを判断できます。
単なる意匠設計だけでなく、申請・検査という台湾特有のプロセスまで視野に入れた設計体制を持つ会社と組むことで、後戻りのないスムーズなプロジェクト進行が可能になります。
意思疎通のミスで設計意図が伝わらない(言葉・文化の壁)
「伝えたつもり」が一番危険
日本企業が台湾の設計会社とプロジェクトを進める中で、最も多いトラブルのひとつが「伝えたつもりだったのに、伝わっていなかった」というコミュニケーションのミスです。
これは、言語の違いというより、文化や業界用語、業務スタイルの違いが原因です。
たとえば、日本では「落ち着いた雰囲気」といえば暗めで木目調を想像しますが、台湾では「落ち着き=シンプルで白っぽい空間」と認識されることがあります。
また、「仮設置で様子を見てから最終調整」といった言い回しも、台湾の現場では「すぐに決めてほしい」というプレッシャーになりかねません。
このように、言葉自体は通じていても、背景にある感覚や常識が違うため、設計意図が誤解されるリスクは非常に高いのです。
日本語が通じても“設計言語”が通じない
台湾の設計事務所の中には、日本語対応が可能なスタッフを擁している会社もあります。
しかし、ここで注意すべきなのは「日本語が話せる=日本の設計文化を理解している」とは限らないという点です。
たとえば、日本特有の「矩計図(かなばかりず)」や「通り芯(とおりしん)」といった概念は、台湾では使われないため、意味が伝わっていなかったり誤解されていることも多いです。
さらに、設計変更に関しても「設計変更指示書」を作成して進める文化はあまり根付いていません。
このため、日本語でコミュニケーションできる安心感に頼りすぎず、「共通の設計用語辞書」や「定義共有シート」を作成し、プロジェクト初期に互いの共通認識を確認することが非常に効果的です。
台湾現場で通じる伝え方とは?
台湾の設計・施工現場では、文章や口頭の指示よりも「ビジュアル」での共有が最も伝わりやすい手段です。
たとえば、仕上げ材の指定に関しても、文字だけで「オーク材風フローリング」と伝えるより、実物サンプルや類似店舗の写真を提示した方が、断然スムーズに意図が伝わります。
また、「完成イメージ」については、パースやスケッチを活用するだけでなく、「NG例」や「避けたい仕様」も併せて提示するのがポイントです。
台湾では「どこまで自由にやってよいのか」が設計者の裁量に委ねられているため、「これは絶対NG」「ここはお任せ」と線引きすることで、認識のズレを防ぐことができます。
視覚資料とイメージ共有の重要性
特に重要な部分に関しては、パース、スケッチ、参考写真、仕上げサンプル、モックアップなど、あらゆる視覚資料を駆使することが推奨されます。
日本では詳細図で伝える内容も、台湾では「見た目」で理解されることが多いため、「図面+イメージ資料」のセットで指示を出すことが標準対応となりつつあります。
以下は、視覚資料の活用法の例です:
| 内容 | 視覚資料の例 |
| 店舗全体の雰囲気を伝えたい | 完成予想パース、過去実績写真 |
| 什器や造作の仕上げ指定 | 実物サンプル、色見本、素材サンプル |
| NGの方向性を共有したい | 他社のNG事例、望ましくないデザインの写真 |
| 納まりの意図を明確に伝えたい | 詳細図に加え、納まり写真や断面スケッチ |
このように、言葉を補完する形で視覚資料を用いることで、意思疎通のズレを大幅に減らすことができます。
言語の壁を超える「通訳的デザイン監修」
日本企業が台湾で設計を進める際には、「設計通訳者」のような存在が極めて重要になります。
これは、単に言語を翻訳するのではなく、「文化」「品質基準」「期待値」まで翻訳し、双方の理解をつなぐ橋渡し役です。
この役割を果たせる人材がプロジェクトに関わるかどうかで、成功確率は大きく変わります。
設計監修という立場で、日本企業の意図を台湾の設計会社に正確に伝え、同時に台湾の現場事情を日本側にリアルに伝える存在が、両国間の信頼構築に不可欠なのです。
今後、台湾での出店を予定している企業にとって、単に「翻訳できるスタッフ」ではなく、「設計文化を理解し調整できる通訳的監修者」をパートナーに持つことが、よりスムーズなプロジェクト運営の鍵となります。
📝まとめ:設計段階で起きる日台トラブル、その本質とは?
日本と台湾、それぞれの文化や慣習、設計に対する考え方の違いが、設計段階におけるトラブルの本質を作り出しています。
日本では「正確な図面と段取りがすべての基礎」とされるのに対し、台湾では「柔軟に動きながら形にしていく」ことが重視されます。
今回紹介した5つのトラブル事例は、すべてそのギャップから生まれるものです。
- 図面未確定のまま工事が始まる
- 合意形成の不十分さが施工トラブルに
- 図面の情報不足が現場判断を招く
- 法規制の理解不足が設計のやり直しに
- 意思疎通のミスが設計意図の誤解を生む
これらはどれも、ほんの少しの配慮と“通訳的存在”の関与、そしてビジュアル共有の工夫で避けられることばかりです。
日台でより良い空間をつくるためには、相手の文化を尊重しつつ、自分たちの当たり前を押しつけない姿勢が求められます。トラブルを「文化の違い」として受け止めるのではなく、「事前の確認と可視化」によって、信頼関係を深めるチャンスと捉えていきましょう。