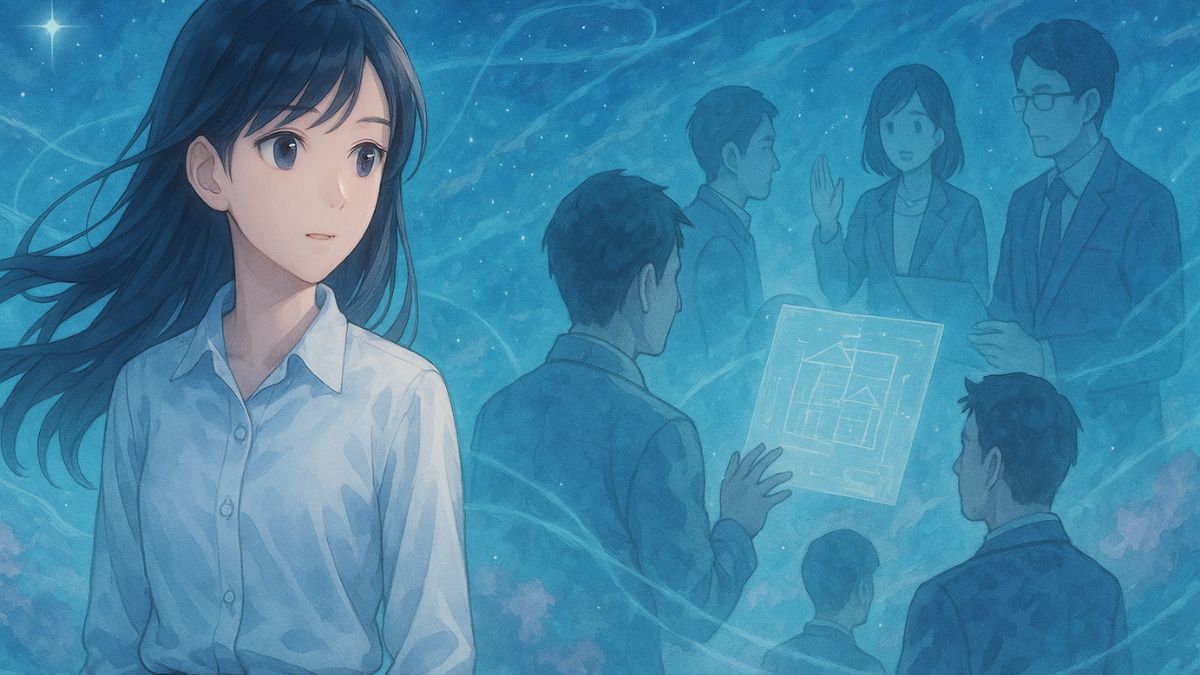日本企業が台湾に進出する際、最初のハードルとなるのが「現地設計会社との初打ち合わせ」です。
一見、同じアジア圏で似た文化を持つように見える台湾ですが、設計の価値観、打ち合わせの進め方、言葉の壁など、その違いは想像以上です。
本記事では、台湾の設計会社と初めて向き合う際に知っておきたい「文化的な違い」や「信頼関係を築くコツ」を、実際の現場経験をもとに解説します。
これから台湾に出店する日本企業の皆さまにとって、安心して一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。
日本と台湾、打ち合わせ文化の大きな違いとは?
会議の進め方にルールがない?台湾式「自由な流れ」
台湾の設計会社との初打ち合わせでまず戸惑うのが、「打ち合わせの進め方が自由すぎる」点です。
日本のように議題や進行役が明確に決まっているスタイルではなく、その場で話題が飛び交う「流れ重視」の傾向があります。
日本企業からすると、「あれ、今なにを決めてるの?」「議事録取らないの?」と不安に思うかもしれません。
しかし、これは台湾の「柔軟性を大切にする文化」の現れです。
アイデアを出し合う場として打ち合わせを捉えているため、進行はラフで、即興的な話が多く、途中で方向性が変わることもあります。
日本側が主導して議題を明確に提示し、アジェンダを事前に共有することで、軸をぶらさずに話を進めることが可能です。
決まったことが「あとで変わる」ことへの覚悟
日本の設計業界では、一度合意した内容は「確定事項」として進行するのが一般的です。
しかし台湾では、初回打ち合わせで決まった内容でも「あとで変更が入る前提」で考えられています。
これは台湾の市場がスピード重視かつ「まずやってみてから調整する」文化であるためです。
つまり、日本のように「設計が固まってから着工」ではなく、「走りながら考える」が普通。
だからこそ、初打ち合わせの内容を過信しすぎず、今後の調整の余地も含めて柔軟に考える姿勢が大切です。
名刺交換や自己紹介は形式的でないことも
台湾では、日本のように名刺交換から丁寧に始める文化はそれほど重視されていません。
もちろん名刺は渡しますが、座ったままで軽く渡す、自己紹介もあっさり、という場面も多く見られます。
それが無礼ということではなく、あくまで「中身重視」という台湾流。
日本側が丁寧なマナーを持ち込んでも構いませんが、相手のラフな対応に驚かず、受け入れる心構えが必要です。
「社長」や「担当者」の役割があいまいな場合も
台湾の中小規模の設計会社では、肩書と実務の役割が一致しないケースが多くあります。
「社長」と紹介された人物が実は営業担当だったり、逆に若手デザイナーが実質的にすべてを仕切っていたり。
日本企業のような階層構造ではないため、「誰が決定権を持っているのか」を初回で見極めることが重要です。
この点を見誤ると、あとで「言った・言わない」のトラブルになりがちです。
なるべく打ち合わせの場では、「この点は誰が決めるのか」を明確に確認しておくと安心です。
信頼よりスピード?短期間での成果を求める傾向
日本の設計会社との関係は、信頼関係を築きながら長期で進めていくのが主流です。
しかし台湾では「まず成果ありき」。
信頼よりも「この人と仕事をすると結果が早く出るか」を重視される傾向があります。
そのため、初打ち合わせの段階で「具体的な実績」や「納期の目安」を提示することが信頼を得る近道になります。
設計イメージ共有の落とし穴とその対策
言葉だけでは伝わらない!ビジュアルが命
台湾の設計会社との打ち合わせでは、「言葉だけで設計意図を伝える」のは非常に危険です。
日本では、細かなニュアンスも「常識」や「空気感」で補える場面が多いですが、文化の違う台湾ではそれが通じません。
そこで必須となるのが、ビジュアルでの共有です。
スケッチ、写真、3Dパース、過去事例などを豊富に用意し、「こんな雰囲気にしたい」という世界観をできるだけ視覚的に伝えることが大切です。
特に、カラーや照明、素材感などは、日本語で説明するより、画像を使った方が正確に伝わります。
「イメージが伝わったつもり」が最大のリスク
よくある失敗が、「相手がうなずいていたから理解してくれたと思った」というケースです。
実際には、台湾側はその場で反論しないだけで、違う理解をしていることも少なくありません。
そのため、打ち合わせが終わったら必ず内容を文字で再確認することが重要です。
図やサンプルを送付し、「このようなイメージで認識あっていますか?」と再確認する一手間が、後々の大きな誤解を防いでくれます。
素材の名前が通じないこともある
日本で「フレキシブルボード」「シナ合板」などといった専門用語を使っても、台湾ではそれが通じないことがあります。
素材の呼び方や流通名が違うため、日本名をそのまま伝えるのではなく、写真付きの資料や英語名で補足することが有効です。
特に天然素材や壁紙の型番など、微妙な差が品質に影響する部分では、現物サンプルの取り寄せがトラブル防止に役立ちます。
「抜け感」や「余白の美学」は伝わりづらい?
日本で大切にされる「余白」「間」「抜け感」などの設計哲学は、台湾の商業空間ではあまり優先されない傾向があります。
台湾では「使いやすさ」「機能性」に加えて「賑やかさ」が重視される傾向にあります。
そのため、こうした美学的な要素を打ち合わせで伝えるには、文化的な背景を交えて丁寧に説明する必要があります。
なぜこの空間に余白が必要なのか、どんな心理効果があるのかを具体的に語れると、設計意図の説得力が増します。
おすすめツール:MIRO、Google Slide、Pinterest
視覚的なイメージを共有するために、例えば以下のようなアプリを使ってみてはいかがでしょう。
- MIRO https://miro.com/ja/ :オンラインホワイトボード
- Google Slide https://workspace.google.com/intl/ja/products/slides/ :— 資料作成
- Pinterest https://jp.pinterest.com/ :イメージ共有
このような機能を使えば、打ち合わせ前に視覚的なイメージが共有でき、双方の理解をすり合わせることができるので、打ち合わせ中の「思ってたのと違う・・・」と感じるリスクを大幅に減らせます。
言語の壁をどう乗り越える?実例に学ぶ工夫
通訳は設計に詳しい人を選ぶのが鉄則
台湾での初回打ち合わせにおいて、最も大きな障害の一つが「言語の壁」です。
設計や内装に関する専門用語を含んだ説明は、一般の通訳では対応が難しい内容が多分に含まれています。
例えば「矩計図」や「巾木」「見切り材」といった日本語の専門用語は、直訳では正確な意味が伝わりません。
同様に、日本語ではよく使われるカタカナ用語は、全く通じないという前提で資料作成と通訳の手配を行うことが必要でしょう。
設計や施工の知識があり、かつ日台双方のビジネス文化に詳しい通訳者を準備することも必要ですが、それ以上に、資料で使われる単語は、この業界の人でない一般の人でも理解できる程度のもので、かつカタカナ用語を極力使っていない資料を作成しておいた方が無難でしょう。
単語だけでなく「意味の背景」を伝える
一般的な日本語の中には、文化的背景を伴う、日本人の心が動くような感覚的な言葉や表現が多くあります。
「和モダン」「ナチュラル志向」などがそうです。
こういった言葉はそのまま訳しても全く伝わりませんので、違う言葉で説明できるなら違う言葉で、この言葉を使いたいなら背景や目的をとにかく丁寧に相手が理解したと納得できるまで説明する努力が必要です。
たとえば「和モダン」は、「日本の伝統素材を用いながら、現代的なデザインで再構成された空間」などと言葉の持つ概念を具体化すると、相手がイメージしやすくなります。
単語の意味を直訳するのではなく、「なぜそうしたいのか」を話すことが真の理解を得る鍵です。
図と絵は「世界共通語」
言語の壁を越える最も有効な方法は、「図と絵」を使うことです。
断面図、イメージパース、レイアウト図などの視覚資料を多用することで、言葉に頼らないコミュニケーションが可能になります。
実際、台湾の設計現場では図を使ったやり取りが日常的です。
日本語の解説がついていても、図や寸法が正確であれば問題なく理解してもらえます。
視覚資料こそが最も確実で誤解のない伝達手段と言えるでしょう。
AI翻訳アプリを過信しないこと
最近では、翻訳アプリやAI同時通訳ツールも進化していますが、建築・設計の専門用語まではカバーできないことが多いです。
特に「仕上げ」「化粧面」「左官」などの専門語は、機械翻訳では意味が変わってしまうことがあります。
したがって、あくまで補助的に使用し、最終的には人の目と耳で確認することが大切です。また、誤解を避けるためにも、「翻訳後の文を自分でも一度読んでみる」ことをおすすめします。
ただし、「仕上げ」と「遊び」は、中国語ではなく台湾語として、この業界では一般的に使われていて、現代日本語の使用方法とほぼ同じです。
日本語でそのまま「仕上げ」「遊び」という言葉を、内装工事の現場で使うと通訳なしでそのまま通じます。
内装工事の現場では日本時代から残っている言葉ですが、一般社会の中では使われることはほとんどないので、通訳できないし、翻訳アプリも対応しない言葉です。
実例:通訳なしで打ち合わせ成功したケース
ある日系ブランドの台湾出店プロジェクトでは、設計担当者が台湾に常駐できず、通訳も同席できないという状況がありました。
しかし、その際には事前に動画付きプレゼン資料と、Google Translateで訳した中国語説明を用意。
また、打ち合わせ後には台湾側の理解内容を中国語で要約してもらい、日本語に再翻訳して齟齬を確認するフローを徹底しました。
結果として、細かなズレはあったものの、大きなトラブルなく初期段階をクリアできた好例となりました。
このように、「ツール+フロー+人の確認」を組み合わせれば、言語の壁は乗り越えられます。
打ち合わせ時に必ず確認すべき5つのこと
① 誰が最終決定権を持っているのか?
台湾の設計会社では、立場と実務の役割が一致しないことが多々あります。
例えば、営業担当が同席していても、最終的な設計判断はデザイナーが行うケース、あるいは逆もあります。
そのため、初回打ち合わせの段階で必ず「誰がこのプロジェクトの決定権を持っているのか」を明確にしましょう。
これにより、以降のやり取りがスムーズになり、「この人に何を伝えるべきか」が整理できます。
② 工程スケジュールの感覚とその管理方法
台湾では「スピード感」が重視され、タイトなスケジュールで物事が進むことが多いです。
ですが、そこには工程管理が緩い傾向もあります。
「来週工事開始です」と急に言われることも珍しくありません。
初打ち合わせの時点で、どのタイミングで図面がFIXされ、発注・施工に移るのかなど、スケジュール管理の流れを細かく確認することが大切です。
ガントチャートのような工程表を共有し、共通認識を持つと安心です。
③ 図面フォーマットと提出方法
台湾では、図面の提出形式にバリエーションがあり、CADやPDFだけでなく、LINEやWhatsAppで画像を送ってくることもあります。
しかも、設計図のレイヤー分けや図面番号の管理が曖昧なケースも多いため、日本側としては非常に戸惑います。
初回打ち合わせで、「正式な図面の提出方法はどうするか」「チェックバックはどう返すか」など、図面のやり取りルールを確認しておくことで、後々の混乱を防ぐことができます。
④ 使いたい素材・設備の調達可否
日本で一般的な建材や設備が、台湾では手に入らない、もしくは非常に高価というケースがあります。
例えば「和紙クロス」「TOTOの特定型番」など、ローカルでの調達が難しいことも。
初打ち合わせの時点で、使いたい素材や設備の候補リストを渡し、それが現地で入手可能か確認することが大切です。
調達可否によって、デザインや予算の見直しが必要になる可能性があるため、早めに確認しておきましょう。
⑤ コミュニケーションのルール
「誰と、何語で、どのツールで連絡を取り合うか」は、最初に必ず決めておくべきポイントです。
LINE、WeChat、メール、電話など、連絡手段がバラバラだとトラブルの元になります。
例えば、「正式な指示はメールで残す」「緊急連絡はLINEで行う」「中国語と日本語の両方で送る」など、運用ルールを明文化しておけば、後の混乱を防ぐことができます。
信頼関係を築くためのマナーと心がけ
お土産よりも「一緒に食事」が信頼への近道
台湾では、ビジネスの関係づくりにおいて「食事」が非常に重要な意味を持ちます。
初回の打ち合わせ後に軽くランチやディナーを共にすることで、一気に距離が縮まります。
日本のように形式的なやりとりよりも、「人として信頼できるか」が重視される文化のため、気軽な食事の場こそが信頼構築の第一歩なのです。
ビジネスの話はさておき、まずは互いを知ることを大切にしましょう。
「ありがとう」を繰り返すよりも「あなたに頼みたい」が響く
日本では感謝の気持ちを何度も伝える文化がありますが、台湾ではそれよりも「あなたにこの仕事をお願いしたい」と直接的に伝えることの方が信頼を生みます。
たとえば、「◯◯さんのデザインセンスを信頼しています」と一言添えるだけで、相手のやる気は大きく変わります。
人間関係が濃い台湾だからこそ、誠意のこもった一言が効くのです。
納得しないまま進めない
台湾側がYESと言っても、必ずしも納得しているとは限りません。
とくに、日本側の意見が強く出ている場合、台湾のスタッフが遠慮して本音を言いづらいことがあります。
そのため、打ち合わせでは「本当にこれでいい?」と何度も確認し、相手の表情や反応をよく観察することが必要です。
言葉よりも態度を大事にするのが台湾流です。
決めつけよりも提案型で話す
「これが正解です」と断言するよりも、「こんな案もありますが、どう思いますか?」という提案型の話し方が好まれます。
台湾では、フラットで意見が出しやすい雰囲気が重視されるため、日本のような「一方的な指示」に近い話し方は敬遠されがちです。
設計内容についても、「こういうコンセプトで進めたいが、ローカルに合うと思いますか?」というスタンスで臨むと、協業の空気が生まれやすくなります。
約束を守る、それだけで信頼は積み上がる
最後に、やはり一番の信頼構築の方法は、「言ったことを守る」ことです。
納期、内容、支払い──どれも小さなことを確実に守ることで、台湾の設計会社からの信頼は格段に上がります。
口約束が多い台湾ですが、それでも「約束を必ず守る日本企業」として評価されることは大きな差別化になります。
まとめ
台湾の設計会社との初打ち合わせは、日本とはまったく異なる文化や感覚との出会いです。
しかし、それを「難しい」と感じるか「可能性」と捉えるかで、プロジェクトの成果は大きく変わります。
ポイントは、相手を尊重しつつ、日本式の信頼構築をベースにしながら、柔軟に台湾流を受け入れていくこと。
そして、初回の打ち合わせこそが「今後の協業の空気」をつくる大事な場面であることを忘れてはいけません。